
こんにちは!猫助です。
今回の記事では、ファッション業界の巨匠である【ユニクロとGU】の違いからマーケティング戦略について学んでいこうを思います。
両ブランドがファーストリテイリングの傘下にあることは皆さんもご存知かと思いますが、具体的に何が異なっており、何のために二つのブランドを展開しているのかを知っている人は少ないかと思います。
今回の記事では、二つのブランドをマーケティング戦略の観点から比較しながら深掘りしていこうと思います!!
この記事を読むと、、、
✔️ユニクロとGUの違いがマーケティング戦略の観点で説明ができるようになる
✔️ファッションブランドのマーケティグ戦略について説明ができるようになる
✔️ファーストリテイリングの戦略がわかる
ユニクロとGUはなぜ“似て非なる存在”なのか?

「ユニクロ」の神戸三宮センター街旗艦店をパトロール! 「ギャップ」跡地に出店
ユニクロとGU——どちらも日本を代表するアパレルブランドであり、ファーストリテイリングという同じ企業グループに属しています。価格帯も比較的安価で、シンプルなデザインが多く、一見すると「ほとんど同じブランドなのでは?」と感じる人も少なくありません。
しかし、実際に店舗に足を運んでじっくりと比較してみると、商品の雰囲気や、店内の音楽やレイアウトなど、あらゆる部分に違いを感じるはずです。
この違いは偶然ではなく、マーケティング戦略に基づいて明確に意図された“差別化”です。
まずは、軽くどのような違いがあるのかを見ていきましょう。
ユニクロとGUはどちらもファーストリテイリング傘下
ユニクロとGUは、いずれも株式会社ファーストリテイリングが展開する自社ブランドです。つまり、ユニクロとGUは“競合関係”ではなく、“兄弟ブランド”にあたります。
ファーストリテイリングは、国内アパレル市場において圧倒的なシェアを誇り、ユニクロを中核に据えながら、GUを“別軸の戦略ブランド”として運営しています。
この二つのブランドを別々に運営しながら、異なるターゲット層やニーズに対応することで、市場全体をカバーする戦略をとっているのです。
つまり、はじめからユニクロとGUは「違っていて当然」であり、意図的にマーケティング戦略上の役割分担を担っている関係と言えます。

ユニクロでも十分大きく市場をとっている印象でしたが、さらに多くの範囲の市場シェアを獲得しようとしているんですね…
ユニクロとGUは価格帯や外見は近いが、店舗に違和感?
ユニクロもGUも、比較的安価なカジュアル衣料を提供しており、商品ジャンルも「ベーシック」「デイリーウェア」が中心です。そのため、価格帯や商品カテゴリだけを見ると、両者は非常に似通っているように見えます。
しかし、実際に店内に入ってみると、そこには明確な違いが存在します。
ユニクロは白や木目調を基調とした落ち着いた内装で、静かなBGMが流れ、整然と並べられた商品棚やゆとりある導線が特徴です。
一方GUは、明るい照明・ポップな色使い・テンポの速いBGMとともに、若干密度の高いレイアウトでトレンド感のある商品を目立つように配置しています。
この「違和感」の正体は、まさにマーケティングにおける“顧客体験設計(CX)”の違いです。両ブランドは同じカテゴリの商品を扱いながらも、「誰のために、どんな空間で、どんな印象を与えるか」がまったく異なるのです。
つまり、価格やアイテムの類似性に騙されず、ブランドとしての“設計思想”を見抜くことが、両者の違いを理解する鍵になります。

店舗のテイアウトの「密度」が違うことに気づいた時はハッとしました。
ユーザーが店舗回遊をする際の感情が少しのレイアウトの違いでこんなにも異なるのかと感心しました。
このような違いに直ぐに気づける人間になりたいですね…(ユニクロとGUを5往復くらいしてやっと気づきました笑)
ユニクロとGUのターゲティングとポジショニングの違いを比較

前章では、ユニクロとGUが同じグループ企業でありながら、あらゆる面で異なる「印象」や「体験」を提供していることを紹介しました。では、この“違い”はどのように意図的に作られているのでしょうか?
マーケティングの基本である「STP戦略」において、ターゲティング(誰を狙うか)とポジショニング(どう見せるか)は、ブランドの方向性を決める重要な要素です。
このセクションでは、ユニクロとGUのマーケティング戦略を、特にターゲティングとポジショニングの違いに注目して比較していきます。
ユニクロは「全世代×ミニマル×グローバル」
ユニクロのターゲットは、ひとことで言えば「誰にでもフィットする服を、誰にでも届く価格で提供する」こと。
つまり、年齢・性別・国籍を問わないという、極めて広いターゲティングがなされています。
例えば、ラインナップを見てみると、無地のTシャツ、シンプルなパンツ、機能性に優れたインナーなど、装飾性は控えめで、デザインも極力ミニマル。そこに込められているのは、「主張しないことが、最大の魅力になる」という思想です。
ビジネスマンが好んで着る無地のTシャツなどが良い例ですね。
ユニクロは、ファッション性よりも機能性・品質・着回しやすさを重視し、あらゆる人が“普段使い”として使えるベーシックウェアを展開しています。これにより、ファッションに関心のある層だけでなく、「服にこだわりがないけど失敗したくない」という層にも選ばれるのです。
また、グローバル展開を積極的に進めるユニクロにとって、ミニマルで汎用性の高いデザインは、文化や価値観の異なる国々でも通用する“普遍的な服”として機能します。だからこそ、ニューヨークでもパリでも、東京とほぼ同じ商品ラインが並んでいるのです。
つまり、ユニクロの戦略は「すべての人にちょうどいい」を設計すること。
その結果、“尖らないこと”がむしろ強さになるという、ブランドとしては珍しい立ち位置を確立しているのです。

明確な尖りがなくても世界的なブランドになってしまうそのマーケティング戦略性に脱帽です。
GUは「若者×トレンド×スピード勝負」
ユニクロが“すべての人に合う服”を目指しているのに対して、GUは「今の若者が、今欲しい服を、今すぐ買える」ことを重視しています。
つまり、明確にZ世代やミレニアル世代をターゲットに設定し、スピード感とトレンド感で勝負するブランド**です。
GUの店内には、毎週のように新作が並び、SNSで話題になったアイテムや旬のカラー・シルエットがすばやく反映されています。
流行が変われば即座に売場が変わる。これは「ファストファッション」というよりも、“リアルタイムファッション”と言ってもいいほどの柔軟さです。
価格帯もユニクロよりさらに手頃に設定されており、トレンドを気軽に試したい10代~20代前半の層にとって、「失敗しても痛くない価格」は心理的ハードルを下げる重要な要素です。
また、GUはSNSでのマーケティングも積極的です。人気インフルエンサーやYouTuberとのコラボレーション、店舗内に設けられた「映える」ディスプレイなど、ブランド全体として「拡散されること」を前提に設計されています。
つまりGUは、「ファッションは自己表現だ」と考える若者に向けて、スピード・価格・話題性という3つの武器で攻めているブランド。
ユニクロが“失敗しない服”を提供するのに対して、GUは“遊べる服”“試せるファッション”を提供しているのです。
このようなスタイルファッションブランドを極限まで突き詰めると「SHEIN」のようになりますね。
「安い」けど意味が違う、ユニクロとGUの価値提案
ユニクロとGUのどちらも、価格帯は「安い」と言われることが多いブランドです。しかしこの「安さ」は、単に数字の話ではありません。どちらも安価に見えて、提供している“価値の内容”がまったく異なります。
ユニクロの安さは、品質や機能性とのバランスによって“コスパ”としての価値を成立させています。
たとえば、ヒートテックやエアリズムといった独自素材、長期間着られる耐久性、万人に馴染むデザイン。
ユニクロの顧客は、価格の安さに加えて「このクオリティでこの値段なら納得」と感じているのです。
一方GUの安さは、トレンドアイテムを気軽に取り入れるための“試しやすさ”に価値があると言えます。
GUを訪れる顧客は、「今の流行を低コストで試したい」「毎週新しいコーデを楽しみたい」と考えており、そのスピード感と入れ替わりの早さに魅力を感じています。
つまり、同じ“安い”でも、ユニクロは「長く使える安さ」、GUは「今を楽しむ安さ」。
コストパフォーマンスとトレンドチャレンジ、という異なる方向から価値を設計しているのです。
ファッションという一時的な価値に時間軸を取り入れて、違いを生み出しているということです。
この違いを理解すると、「似たような商品があるようで、選ばれる理由はまったく違う」という両ブランドの戦略的な住み分けが見えてきます。

こうやって具体的に企業のマーケティング戦略を分析していくと、自分の普段の生活の視点がかなり変わっていきますね。
私が関わってきた優秀なマーケターたちはこのような視点で普段から生活していました。
その生活楽しいの?笑と思っていましたが、自分の生活圏内全てが学習の場になり、それを楽しみながらできるというのは案外悪く無いものです笑
ユニクロとGUの両ブランドが共存できる理由とは?

ここまで見てきたように、ユニクロとGUは同じ企業グループに属しながら、異なるターゲット層、異なる価値提供、異なる戦略を展開しています。
では、「似ているようでまったく違う」この2つのブランドは、なぜ市場で共存できるのか?
そして、なぜファーストリテイリングは2ブランドを分けて運営する必要があるのか?
このセクションでは、カニバリゼーション(市場の奪い合い)を避けながら、ブランド同士が戦略的に住み分ける方法について考察していきます。
ユニクロとGUはなぜカニバリせずにうまくやれているのか?
通常、同じ企業グループ内で似た商品カテゴリを扱うブランドを複数展開すると、「カニバリゼーション(自社ブランド間の競合)」が問題になります。
しかし、ユニクロとGUは、同じアパレル領域にいながら、むしろ互いのブランド価値を損なうことなく共存できています。
その理由は、両ブランドが明確に異なるターゲット層を狙い、異なる購買動機を刺激するように設計されているからです。
ユニクロは、「汎用性・品質・日常着としての信頼性」を重視する全年齢層に向けたブランド。
一方GUは、「流行を取り入れたい・毎週新しい服を楽しみたい」という若年層の感性に刺さるように設計されています。
さらに、ユニクロは“ベースを整える服”、GUは“アクセントを加える服”といったポジショニングも取られています。
たとえば、「ユニクロの白Tに、GUのカラーパンツを合わせる」というように、1人のユーザーが両ブランドを目的別に使い分けることすら可能なのです。
こうしたターゲットと役割の分離が、ブランド同士の衝突を防ぎ、むしろグループ全体としての市場支配力を高める構造を作っています。
カニバリしないというよりむしろ、ユンクロとGUの両ブランドを使う人間を生み出しているのだから、互いに高め合う構造になっていると言えますよね。
ファーストリテイリンググループ戦略としての「住み分け設計」
ファーストリテイリングの経営戦略には、「一社で複数の市場ニーズを満たす」という明確な意図があります。
ユニクロは機能性と品質に優れた定番服で、国内外問わずあらゆる年齢層に受け入れられる“グローバルスタンダード”なブランド。
一方GUは、国内の若者を中心に「安く・早く・流行に乗れるファッション」を提供する、“スピードと感性”のブランドです。
このように、一つの企業が異なる戦略軸をもつ複数ブランドを展開することによって、特定のブランドでは拾いきれないニーズを包括的に取りにいく。それがファーストリテイリングのマーケティング上の強さとなっています。
また、複数ブランドを展開することには、もうひとつ大きなメリットがあります。
それは、ユニクロで得られたグローバルな生産・物流ノウハウを、GUのトレンド展開に活かせるというシナジー効果。
個別ブランドが独立して動いているのではなく、グループ全体で戦略的にリソースを共有しながら、それぞれのブランド価値を最大化しているのです。
ユニクロはオムニチャネル戦略の成功例として知られているくらいブランド力以外の強みも持っています。これをGUにそのまま転用できるのはかなりの競合優位性になります。詳しくは以下の記事で触れているので併せてインプットしておくことをお勧めします!
まとめ:ユニクロとGUに学ぶ「ターゲティング」の本質
ユニクロとGUは、見た目や価格帯が似ているようで、実はまったく異なる戦略のもとで運営されているということはよくわかりました。その違いの本質は、単なるブランドイメージではなく、「誰に、どんな価値を届けるか」というマーケティングの根幹にあります。
ユニクロは、全年齢・全世界に通じる普遍的な品質と機能性を提供することで、長く着られる“定番服”を提供しています。
一方GUは、若者の感性やスピード感に応えるトレンドファッションを、手に取りやすい価格で届けるブランドです。
このように、明確なターゲティングとポジショニングによって“安くて似た服”を売っているようで、実は全く違う価値を提供しているのです。
ビジネスにおいても、自分の提供する商品やサービスが「誰の、どんな悩みを解決するのか」を明確にしなければ、価格競争に埋もれてしまいます。
ユニクロとGUに学べるのは、「価格ではなく、相手に届ける価値の設計がブランドを分ける」というマーケティングの本質です。
商品が似ていても、ターゲットと価値の軸をズラすことで市場は共存できる。
この考え方は、どんなジャンルのビジネスにも応用できる、大きなヒントになるはずです。
良質なインプット習慣には「Schoo(スクー)」がおすすめ!!(PR)
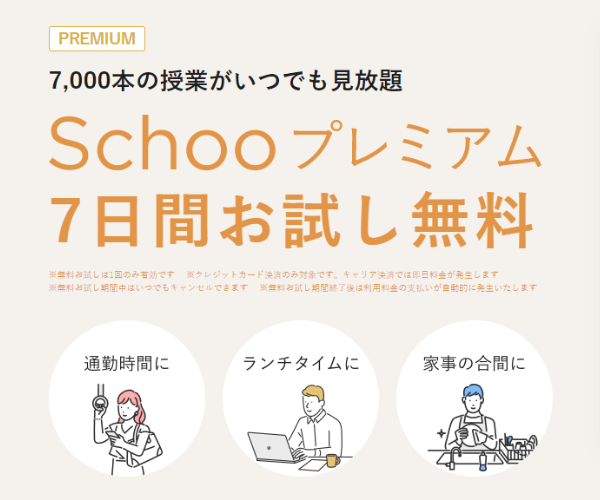
\ 今なら7日間無料!/
【Schoo】で今すぐ学ぶ【Schoo(スクー)とは?】
✅「今日から役立つ実践スキル」が学べるライブ動画コミュニティ
✅ライブ授業、チャット機能で双方向で学べる
✅8000本以上の授業で多様なジャンル
✅「一生学べる学校」をすべての社会人が学べるコンテンツを配信
\ 今なら7日間無料!/
【Schoo】で今すぐ学ぶ
猫助のインプットアカデミーでは主にマーケティング戦略を中心としたものにフォーカスしていますが【Schoo】ではビジネスの基礎知識から、データ分析などの専門的知識までを網羅的にインプットできます!


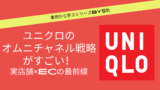


コメント