
こんにちは!猫助です。
今回の記事では、飲食業界の巨匠である【スターバックスコーヒー(通称スタバ)】様からマーケティング戦略について学んでいこうを思います。
皆さんの中でも日頃からスタバに通っている人は多いと思います。
私も、朝スタバでコーヒーを購入し、退勤時にワンモアコーヒーでもう1杯飲むという生活を続けています。
そんな生活の中である日私は気づきました。家の近くにあるドトールの方が安いのに、なぜスタバに行くんだろう?優秀なビジネスマン、学生の皆様もそう思ったことがあるのではないでしょうか。
そこで、今回は「値段が高くてもスタバに通ってしまうスタバのブランディング戦略」について深ぼっていこうと思います!
この記事を読むと、、、
✔️ブランディングについて理解を深められる
✔️ブランド戦略を実践するためのリアルな知識が得られる
✔️スターバックスのマーケティング戦略を理解できる
ブランディングとは何か?ー「価格以上の価値」を作る力
「ブランディング」と聞くと、多くの人が「ロゴ」や「デザイン」「CM広告」などをイメージするかもしれません。しかし、マーケティングにおける本質的なブランディングとは、顧客の頭の中に“企業や商品に対する印象”を築く行為です。ロゴやデザイン、CM広告はそのための手段に過ぎないのです。
また、ブランディングの目的は、単に「商品を売る」ことではありません。他社と差別化し、顧客が“価格以上の価値”を感じて選び続ける理由をつくることにあります。
たとえば、同じようなコーヒーでも、「スターバックスで買いたい」と思わせるのは、まさにブランディングの力です。これは、商品のスペックや価格といった“目に見える価値(機能的価値)”ではなく、居心地のよさや安心感、オシャレ感といった“無形の価値(情緒的価値)”が大きく影響しています。
つまり、ブランディングとは「選ばれる理由を設計するマーケティング戦略」なのです。ブランド価値が高まることで、商品価格が高くても顧客は納得して購入し、リピーターにもなりやすくなります。
このように、ブランディングは単なる装飾ではなく、企業の売上や信頼、長期的成長に直結するために必要な経営戦略であるのです。

オシャレだからカッコつけてスタバ使っちゃいますよね…
私だけですか…?笑
まさに、スターバックスのブランディング戦略の術中にはまっていますね。
スタバのブランド戦略とは?“コーヒー”ではなく“体験”を売る

スターバックスが展開するブランド戦略は、単に「コーヒーを売る」ものではありません。実はスタバのマーケティングの核にあるのは、“商品”ではなく、“体験”を売る”という発想です。
スタバの店舗に入ると、落ち着いた音楽、木目調の内装、笑顔の店員、名前を呼んでくれる接客など、五感すべてに働きかけるような空間が用意されています。これは、単にカフェという枠を超えて、「日常の中のご褒美」や「自分を大切にする時間」といった体験価値を提供しているのです。
また、スターバックスは“サードプレイス”(第三の居場所)というコンセプトを打ち出し、自宅でも職場でもない「居心地のよい空間」をブランディングの柱に据えています。これは顧客にとって、価格では測れない価値を感じさせる大きな要因になっています。
このような体験型マーケティングによって、スタバは「高くても選ばれる」存在となっています。同じコーヒーでも、スタバで飲むことに意味がある――それこそがブランド戦略の成功の証です。
顧客は単に「カフェイン」を求めているのではなく、「その場所で過ごす時間」や「ブランドとの一体感」に価値を感じているのです。
それでは、以下で詳細を分析していきます。
スタバはサードプレイス戦略で居場所をデザインする
スターバックスのブランド戦略の根幹にあるのが、「サードプレイス(Third Place)」という考え方です。これは、“家庭(ファーストプレイス)”でも“職場や学校(セカンドプレイス)”でもない、第三の居場所を意味します。
日常の中でちょっと一息つける、誰にも干渉されずに自分らしくいられる、そんな空間をスターバックスは意識的にデザインしています。たとえば──
- 木の温もりを感じる内装
- Wi-Fiや電源完備で長居しやすい環境
- 混雑していても“落ち着ける雰囲気”
- 名前を呼んでくれる接客など、個人への配慮
これらの要素は、コーヒーそのものの味とは関係ありません。しかし、これこそが「スタバを選ぶ理由」になっているのです。
また、日本では「一人で気軽に入れる場所」としても重宝されています。特に若い世代やリモートワーカーにとっては、スタバは“孤独にならない孤独”を提供してくれる空間でもあります。
この「サードプレイス」という概念は、ただの空間提供ではなく、顧客の感情や心理に寄り添ったブランディング手法です。他社が真似しづらい“居心地のよさ”を構築することで、スターバックスはコモディティ化しがちなコーヒー市場で、確固たる地位を築いているのです。
体験価値の提供:スタバは商品以上の“気分”を売る
スターバックスが売っているのは、決して「コーヒー」という商品だけではありません。むしろ、より重要なのはその一杯を通して得られる“気分”や“雰囲気”、つまり体験価値です。
マーケティング用語で言うところの「体験価値(カスタマー・エクスペリエンス)」とは、顧客が商品やサービスに触れる中で得られる感情や印象、満足感を指します。スタバではこの体験価値の設計に、極めて戦略的な工夫が施されています。
たとえば、
- 季節ごとに変わる限定メニュー
- 店員との軽い会話や笑顔
- 写真映えするカップデザイン
- アプリを使ったスマートな注文体験
これらすべてが「顧客に特別感を与える体験」として計算されているのです。
また、スタバの商品価格は決して安くありません。にもかかわらず多くの人がリピートするのは、「ただのコーヒーを飲みに来ているわけではない」からです。疲れた日にはちょっと贅沢を、自分へのご褒美を、という“感情消費”のニーズを的確に捉えているのです。
このような戦略は、「モノ消費」から「コト消費」へと価値観が変化する現代において、非常に有効です。スターバックスは、商品ではなく“ストーリーや気分”を売ることで、価格以上の納得感を提供しているのです。

スタバの新作が出たら・スタバの限定商品が出たら学校、職場の帰り道に寄ろう。
そんな流れができている人は多いのではないでしょうか?
これは、日常生活の中にスターバックスを組みこむブランド戦略なのです。
ただ単に限定商品や新作を飲むのではなく、それを友人や家族と共に楽しむという体験を提供しているのです。
プレミアム価格の戦略:「納得感ある高さ」の設計

「スタバは高い」と感じたことがある人は多いでしょう。私もそのうちの1人です。
コンビニや他のチェーンと比べても、同じコーヒー1杯で数百円の価格差があります。それでもなお、多くの人がスターバックスを選び続けるのはなぜでしょうか?
ここでは、スターバックスがどのように「高くても納得される価格」を実現しているのかを、マーケティング視点で解説していきます。
あえて安売りしないスタバのポジショニング戦略
その理由の一つが、「納得感のある体験によるポジショニング戦略」です。
マーケティングにおけるポジショニングとは、顧客の頭の中で「このブランドは〇〇だ」と思わせる立ち位置を築くことです。スターバックスは、「高級だけど親しみやすい」「落ち着ける」「気分が上がる」といった“上質感 × 日常感”の絶妙なポジションを確立しています。
これは、「価格が高い=質が高い」という心理効果(※価格品質の連想)も活用しており、あえて安売りをせずに「高くても、それだけの価値がある」と思わせる設計がなされています。
さらに、ポイントアプリや限定メニューの存在も、「この価格でも体験として得られるものがある」と感じさせる材料になっています。
言い換えれば、スタバの価格戦略は“高くすること”そのものがブランディングになっているのです。
顧客は「コスパ」だけでは動かない。“価格以上の意味”をつくることが、現代のマーケティングには不可欠であり、スターバックスはその成功例といえるでしょう。
ポジショニング戦略については、以下の記事で触れていますので併せてインプットしていきましょう!
“価格が高いほど良い”という心理効果の活用
実は人間の心理には、「価格が高いものは良いものに違いない」というバイアスがあります。皆さんも日常生活で、値段を指標に品質を判断することは多いのではないでしょうか?
今日は良いカレーを作りたいから少し高いゴールデンカレーを買ってみよう。贈り物だから少し高めのネクタイをプレゼントしよう。などと考えた人も多いのではないでしょうか?
スターバックスはこの価格品質連想(price–quality inference)を巧みに活用し、「高い=上質な空間やサービスを提供している」と感じさせています。
このように価格そのものがブランディングの一部として機能しており、安売りを一切しないことがブランドの“格”を保つ手段にもなっているのです。
つまり、「高くてもスタバでコーヒーを飲む」というより、むしろ「高いからスタバでコーヒーを飲む」という表現の方が正しいのかもしれません。
価格そのものがブランドの一部になる
スターバックスでは、割引やセールを行うことがほとんどありません。それでも多くの顧客が足を運ぶのは、「安くないけれど、それに見合う価値がある」と感じているからです。
更に前述した通り、「高いからスタバでコーヒーを飲む」というような心理状態をブランディングによって作り出しているからです。
このように、スタバにとって価格は単なる数字ではなく、ブランドイメージを構成する重要な要素となっています。価格帯が高めであることが、逆に「ここで過ごす時間は特別」「選ばれた空間にいる」というブランド体験そのものを強化しているのです。
また、公式アプリを活用したスターバックスリワードやモバイルオーダーなどの機能も、利便性やパーソナライズの価値を追加し、価格に見合った体験を設計しています。これにより、単に「高い商品」ではなく、「納得して選ばれるブランド」としての地位を保ち続けているのです。
つまり、価格に見合った付加価値を提供する点において、ブランド力のみに頼らないスタバのマーケティング戦略が垣間見えるという訳です。
顧客を離さないスタバの仕組み:リワードプログラムとアプリ戦略

スターバックスが「高くても選ばれるブランド」であり続けられるのは、価格や店舗体験だけではありません。
顧客を継続的にブランドと結びつける仕組み、すなわちリテンション戦略が非常に優れていることも大きな要因です。
このセクションでは、スターバックスが展開しているリワードプログラムやモバイルアプリの活用を通じて、どのように顧客との関係性を深化させ、ブランドロイヤリティを高めているのかを解説します。
スターバックスリワード:習慣化を促すポイント設計
スターバックスが顧客の再来店を促す仕組みのひとつが、「スターバックスリワード(Starbucks® Rewards)」というポイントプログラムです。ドリンクやフードを購入するたびに「スター(ポイント)」が付与され、一定数を集めることで、フリードリンクチケットなどの特典と交換できます。
このリワード制度は、単なるポイントカードではありません。マーケティングの観点から見ると、“顧客の行動を習慣化させる設計”が施されています。「あと数ポイントで特典がもらえる」という状況になると、人は無意識にもう一度利用したくなる——これは心理学で言うツァイガルニク効果にも通じるものです。
さらに、スターバックスリワードは、アプリと連携することで顧客が自身のポイント状況をいつでも確認できる仕組みになっています。これにより、ブランドとの接点が日常的に生まれ、スタバに“つながり続ける”感覚が強まります。
このように、顧客との関係性を「点」ではなく「線」でつなぐことが、スターバックスのブランディングをより強固なものにしているのです。

もちろん、ポイントをつければ習慣的に利用するという単純な話ではないです。
あくまでもこれは仕組みにすぎず、ブランディングが上手くいっていることが大前提で、最後の一押しとしての戦略なのです。
習慣化マーケティングについては、以下の記事で触れているので併せてインプットしておくことをお勧めします!
モバイルアプリの活用:UXとパーソナライズの強化
スターバックスが提供するモバイルアプリは、単なる注文ツールやポイント管理機能を超えた、顧客体験(UX)そのものを向上させるマーケティングツールとして機能しています。
まず特筆すべきは、モバイルオーダー&ペイの存在です。混雑時でも並ばずに商品を受け取れるこの機能は、スタバが目指す「快適な体験価値」の体現そのものです。さらに、アプリ決済とリワード機能が統合されており、利用者はストレスなくサービスを享受しながら、自然とポイントを貯めていく仕組みになっています。
また、スターバックスアプリでは、ユーザーの購買履歴や行動データをもとに、好みに応じたドリンクの提案や限定クーポンの配信が行われています。これはマーケティングでいうパーソナライズ戦略であり、何も考えずに利用しているのに自分の好みに合った購買体験が無視意識に設計されているのです。
つまりスタバは、アプリというデジタル接点を通じて、個々の顧客との関係を深化させながら、ブランド体験の質そのものを高めているのです。これは、現代におけるブランディングの最前線を示す好例と言えるでしょう。
まとめ:スタバに学ぶ「高くても売れる」ブランドづくり
ここまで、スターバックスのマーケティングとブランディング戦略を通じて、「高くても売れる」仕組みの裏側を紐解いてきました。
スターバックスは、単なる商品価値ではなく、空間・体験・感情といった“無形の価値”を重視することで、他ブランドには真似できないポジショニングを確立しています。
価格競争に巻き込まれず、それでも多くの人に選ばれ続ける理由は、次のようなポイントに集約されます。
✅ブランディングによって「選ばれる理由」を設計していること
✅商品そのものより“過ごす時間”や“気分”に価値を与えていること
✅リワード制度やアプリなど、継続的なつながりを仕組み化していること
これらはスターバックスだけの特別なものではなく、どんな商品やサービスにも応用できるマーケティングの原則です。
たとえば、あなたが自分のビジネスや就職活動で「どう選ばれるか」を考える際にも、“スペック”だけで勝負するのではなく、“印象”“体験”“共感”といった感情的価値をどう届けるかが重要になります。
スタバが教えてくれるのは、「売れるものを作る」よりも、「“選ばれる理由”を作ることが、最も強いマーケティング戦略である」ということなのです。
良質なインプット習慣には「Schoo(スクー)」がおすすめ!!(PR)
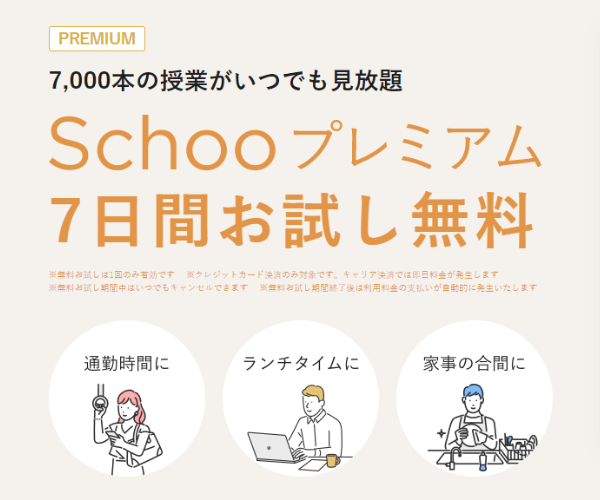
\ 今なら7日間無料!/
【Schoo】で今すぐ学ぶ【Schoo(スクー)とは?】
✅「今日から役立つ実践スキル」が学べるライブ動画コミュニティ
✅ライブ授業、チャット機能で双方向で学べる
✅8000本以上の授業で多様なジャンル
✅「一生学べる学校」をすべての社会人が学べるコンテンツを配信
\ 今なら7日間無料!/
【Schoo】で今すぐ学ぶ
猫助のインプットアカデミーでは主にマーケティング戦略を中心としたものにフォーカスしていますが【Schoo】ではビジネスの基礎知識から、データ分析などの専門的知識までを網羅的にインプットできます!

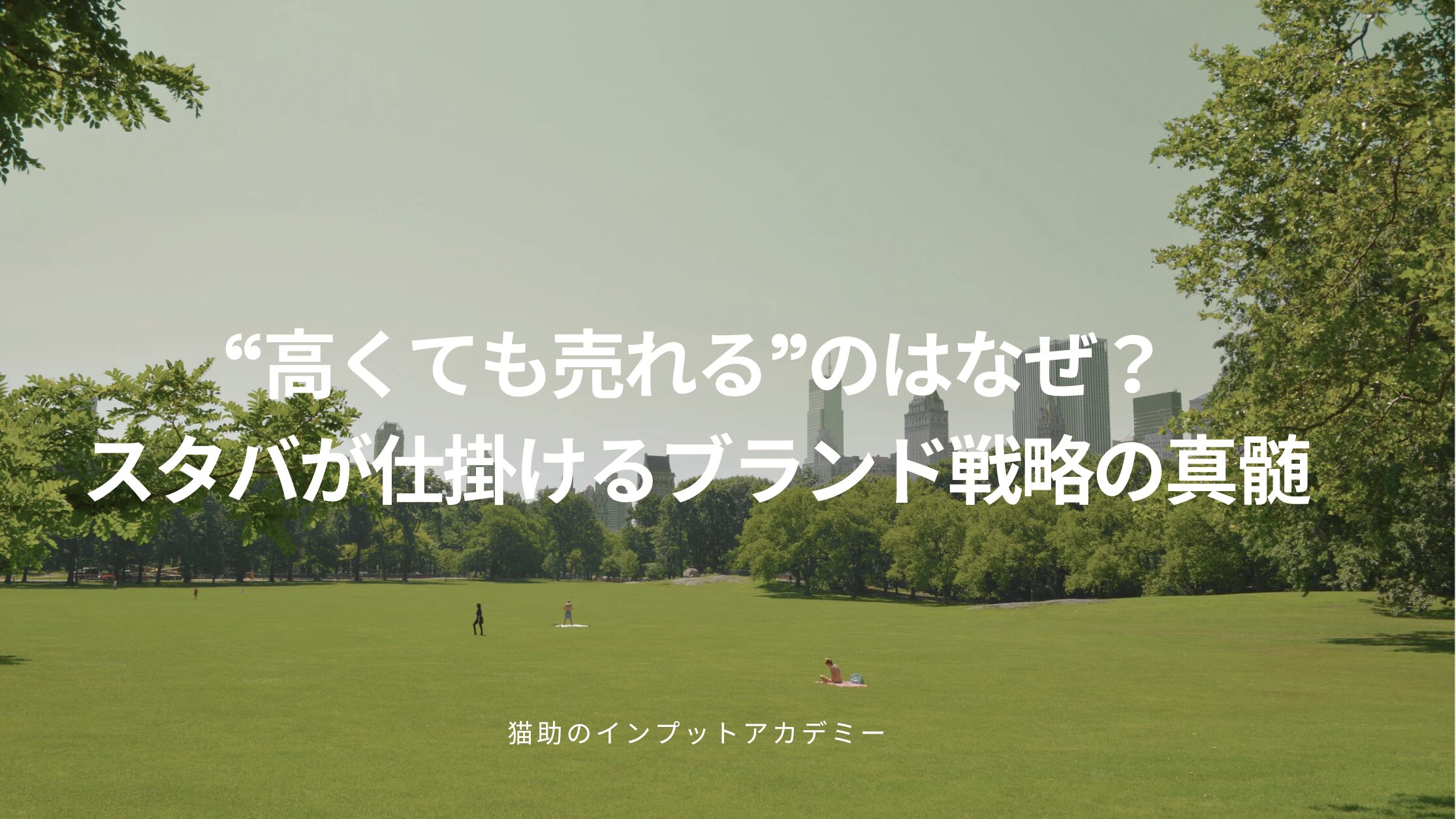


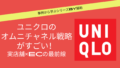

コメント